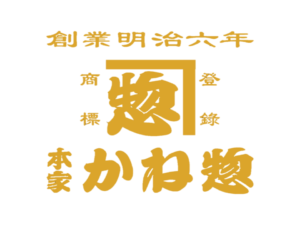こだわり

当店では、焼きの悪いものや焼きムラがあるような商品をお客様にお渡ししないためにも、
お買い上げいただいた包丁を検品の意味で研いでからお持ち帰りいただいております。
研ぎ方について(両刃)

1)砥石を平らにする
まず、砥石の研ぐ面が平らになっているか確認をします。
研ぐ面が平らになっていないと刃先まで当たりませんので、面直し専用の砥石などで砥石を平らにします。

2)片面ずつ研ぐ
平らにしたら、包丁を片面ずつ研いでいきます。砥石が動くようなら、下に雑巾などを敷くと固定されます。
利き手でしっかりと柄を持ち、親指と人差し指で包丁をブレないように支えます。
逆の手の人差し指と中指で刃先を抑え、コイン1〜2枚が入るくらい少し立てて、押すときに力を入れる感覚で研いでいきます。(刃先を抑えた指の下が研げるので、指を少しずつずらしながら研ぎます。)

3)反対側を研ぐ
全体的に刃先に返りが出たらきちんと研げている証拠ですので、そうなったら研ぐ面を裏返して【同じ要領】で研いでいきます。(柄を持つ手は左右変えません。)

4)仕上げ研ぎ(仕上げ砥を使う人のみ)
反対側も全体的に刃先に返りが出たら、仕上げ砥がある場合は先ほどよりも角度を少し立てて両面数回程度軽く研ぐと返りが取れますので、返りが取れれば完成です。(仕上げ砥がない場合や返りが取りきれない場合は新聞紙などで軽く擦れば返りが取れ、お使いいただけます。)
研ぎ方について(片刃)

1)砥石を平らにする
まず、砥石の研ぐ面が平らになっているか確認をします。
研ぐ面が平らになっていないと刃先まで当たりませんので、面直し専用の砥石などで砥石を平らにします。

2)片面ずつ研ぐ
平らにしたら、包丁を片面ずつ研いでいきます。
砥石が動くようなら、下に雑巾などを敷くと固定されます。
利き手でしっかりと柄を持ち、親指と人差し指で包丁をブレないように支えます。
逆の手の人差し指と中指で刃先を抑え、研ぎ刃の角度通りに押すときに力を入れる感覚で研いでいきます。(刃先を抑えた指の下が研げるので、指を少しずつずらしながら研ぎます。)

3)反対側を研ぐ
全体的に刃先に返りが出たらきちんと研げている証拠ですので、そうなったら研ぐ面を裏返して裏面はベタっと寝かせて、同じく押すときに力を入れる感覚で研いでいきます。(柄を持つ手は左右変えません。)

4)仕上げ研ぎ(仕上げ砥を使う人のみ)
反対側も全体的に刃先に返りが出たら、仕上げ砥がある場合は先ほどよりも角度を少し立てて両面数回程度軽く研ぐと返りが取れますので、返りが取れれば完成です。(仕上げ砥がない場合や返りが取りきれない場合は新聞紙などで軽く擦れば返りが取れ、お使いいただけます。)
砥石について
当店では荒砥石→中砥石→仕上げ砥石などいくつもの砥石を使って刃をつけていきますが、ご家庭の場合いくつも砥石を揃えるのは難しいと思います。
そんな方には砥石を購入の際はまず【中砥石】を選んでいただけるといいと思います。
砥石には粒子の細かさによってさまざまな番手の物がありますが、中砥石の中でも【1000番〜1200番】くらいが刃も付けやすいので参考にしてみてください。
もちろん、刃こぼれ状態によっては荒砥石からの方が早い場合がありますので、その場合は荒砥石【200番】くらいの物もあってもいいかも知れません。